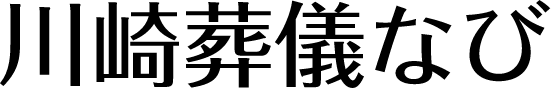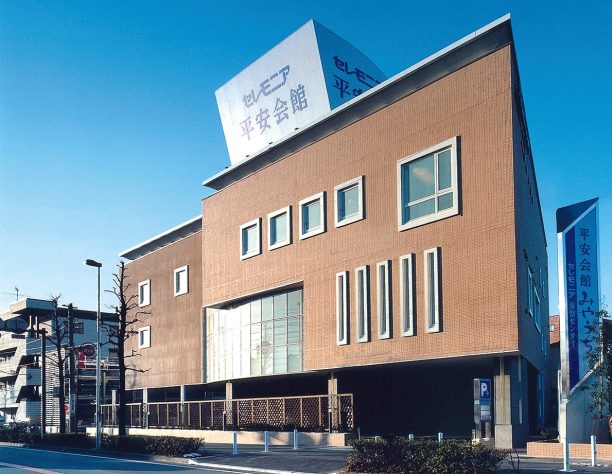身寄りのない人の葬儀は?財産はどうなるの?

近年、核家族化や未婚率の上昇、高齢化社会の進展に伴い、身寄りのない方が増加傾向にあります。もしもの時、身寄りのない方の葬儀はどのように行われるのでしょうか?また、残された財産は誰のものになるのでしょうか?
目次
葬儀について
身寄りのない方が亡くなった場合、葬儀は主に以下のいずれかの方法で行われます。
自治体による葬祭扶助
生活保護受給者など、経済的に困窮している場合は、自治体が葬祭扶助という形で葬儀費用を負担します。この場合、火葬のみが行われることが多く、一般的な葬儀のような儀式は省略されることがあります。葬祭扶助の範囲は自治体によって異なり、最低限の費用しか支給されないことが一般的です。
民生委員や地域住民による葬儀
故人が地域社会とつながりを持っていた場合、民生委員や近隣住民が中心となり、葬儀を行うことがあります。費用は、故人の遺産から支払われるか、関係者の寄付によって賄われます。
地域住民が主体となる葬儀は、故人の人となりを反映した温かいものになることが多いですが、関係者の負担も大きくなります。
葬儀会社やNPO法人による葬儀
近年では、身寄りのない方の葬儀を専門に扱う葬儀会社やNPO法人も増えています。これらの団体は、故人の遺志や宗教観に沿った葬儀を執り行い、遺品整理や供養などもサポートします。
生前に葬儀の契約を結ぶ「生前契約」を結ぶ事で、自身の希望に沿った葬儀を行う事が出来ます。専門の葬儀会社やNPO法人は、身寄りのない方の葬儀に関する豊富な経験とノウハウを持っており、安心して任せることができます。
財産の取り扱い
身寄りのない方が遺産を残して亡くなった場合、その財産は「相続財産管理人」によって管理され、最終的には国庫に帰属します。
相続財産管理人の選任
家庭裁判所は、故人の債権者や関係者の申し立てにより、相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが一般的です。相続財産管理人は、故人の財産を適切に管理し、債権者への弁済や遺産の清算を行います。
財産の調査と清算
相続財産管理人は、故人の財産と負債を調査し、債務の弁済や遺産の清算を行います。
もし、遺言書が発見された場合は、遺言書の内容に従って財産が処分されます。遺言書がない場合は、民法に定められた相続のルールに従って財産が処分されます。
特別縁故者への分与
故人と特別な関係があった人がいる場合、家庭裁判所は、その人に遺産の一部または全部を分与することがあります。
特別縁故者とは、内縁の配偶者や事実上の養子など、法律上の相続人ではないものの、故人と生計を共にしていたり、療養看護に努めたりした人を指します。特別縁故者への分与は、故人と特別縁故者の関係性や貢献度などを考慮して判断されます。
国庫への帰属
相続人が存在せず、特別縁故者への分与も行われなかった場合、残った財産は最終的に国庫に帰属します。国庫に帰属した財産は、公共事業や社会福祉などに活用されます。
生前にできること
身寄りのない方が、自身の葬儀や財産のことで不安を感じる場合、生前に以下の対策を講じることができます。
遺言書の作成
遺言書を作成することで、財産の処分方法や葬儀の希望などを指定できます。遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
専門家と相談しながら、自身の希望に沿った遺言書をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。
死後事務委任契約
葬儀会社やNPO法人と死後事務委任契約を結ぶことで、葬儀、納骨、遺品整理などを委託できます。
死後事務委任契約では、葬儀の種類や費用、納骨の方法、遺品整理の範囲などを具体的に決めることができます。
成年後見制度の利用
判断能力が低下した場合に備え、成年後見人を選任しておくことで、財産管理や生活支援を任せることができます。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。自身の状況に合わせて、適切な後見制度を選択しましょう。
生前契約
近年では、生前契約に対応する葬儀社やお寺が増えています。
葬儀やお墓について、生前に葬儀社やお寺と契約を結んでおくことが可能です。生前契約を結ぶことで、自身の希望に沿った葬儀やお墓を準備することができます。
身元保証サービスの利用
身元保証会社は、身寄りのない方の生活を総合的にサポートしてくれる会社です。
身元保証会社と契約する事で、入院や介護施設への入居時の身元保証人、緊急連絡先、葬儀や納骨に関する事務手続きなどを依頼することが出来ます。
自身の希望に沿った形で最期を迎えるため、身元保証会社の利用も視野にいれることが重要です。
まとめ
身寄りのない方の葬儀や財産の取り扱いは、複雑な手続きが必要となる場合があります。もしもの時に備え、生前から準備をしておくことが大切です。専門家や関係機関に相談しながら、自身の希望に沿った対策を講じることをおすすめします。