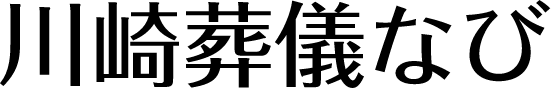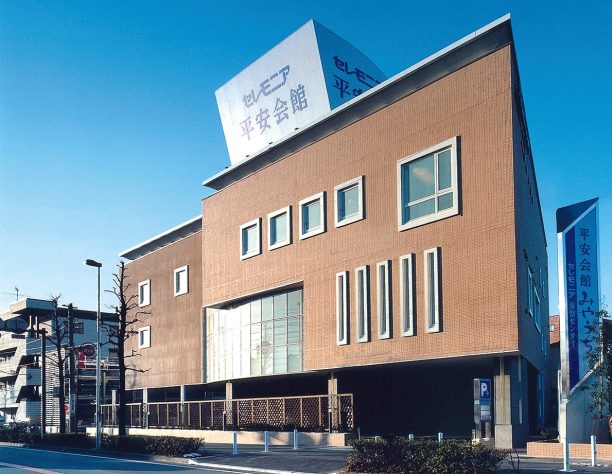お盆っていつ何をすればいいの?地域による違い、期間中に避けるべきことも解説!

お盆は、ご先祖様の霊が子孫のもとへ帰ってくるとされる大切な期間です。日本では古くからこの風習が大切にされており、地域によって時期や過ごし方に違いが見られます。
川崎をはじめとする関東の都市部では7月にお盆を行う地域もあります。内容や時期に地域差が多い行事のひとつですので詳しく解説します。
目次
お盆の期間と一般的な過ごし方
お盆の期間は、多くの地域で8月13日から16日とされています。これは「月遅れ盆」または「旧盆」と呼ばれます。一方、東京や神奈川、静岡、熊本の一部など、都市部では7月13日から16日にお盆を行う地域もあり、こちらは「新盆」と呼ばれます。
沖縄県など、旧暦に基づいてお盆が行われる地域は毎年時期が変動し、9月にずれ込むこともあります。
13日(迎え盆)-ご先祖様の霊を迎える日
午前中に精霊棚(盆棚)の飾り付けやお供え物の準備をします。お墓参りをして、お墓の掃除も行います。
夕方には、ご先祖様の霊が迷わず帰ってこられるように「迎え火」を焚きます。住宅事情で火を焚くのが難しい場合は、盆提灯や白提灯を灯すだけでも良いとされています。初盆(亡くなってから初めて迎えるお盆)の場合は、特に白提灯を飾るのが一般的です。
14日・15日(中日)-ご先祖様をもてなす期間
家族や親族が集まってお墓参りや会食をします。
新盆の場合は、僧侶を招いて法要(読経やお焼香)を行うのが一般的です。
精霊棚のお供え物や水は毎日交換し、ろうそくや線香の火を絶やさないようにします。
16日(送り盆)-ご先祖様の霊を見送る日
夕方には「送り火」を焚き、ご先祖様の霊が無事にあの世へ戻れるよう見送ります。京都の五山送り火や長崎県の精霊流しが有名です。
地域によっては、お墓参りも行い、ご先祖様への感謝を伝えます。
地域によるお盆の風習の違い
お盆の時期が異なる背景には、明治時代の改暦が関係しています。旧暦の7月15日に行われていたお盆が、新暦に変わることで農作業の繁忙期と重なり、時期を1ヶ月遅らせた地域が多かったためです。
また、迎え火・送り火のやり方やお供え物、行事にも地域差があります。
- 精霊馬(しょうりょううま)
東日本ではキュウリやナスに割り箸を刺して作る精霊馬を飾る風習が広く見られます。キュウリの馬には「早く帰ってきてほしい」、ナスの牛には「ゆっくり戻ってほしい」という願いが込められています。西日本では行われない地域もあります。 - 浄土真宗
浄土真宗では、亡くなった人はすぐに成仏するという教えから、先祖の霊を迎えるという習慣がなく、迎え火や送り火は行われません。 - 広島の盆灯籠
広島県では、お墓にカラフルな盆灯籠を飾る風習があります。 - 沖縄の旧盆
沖縄では旧暦に合わせた「旧暦盆」を重視し、地域によっては「シチグヮチ」と呼ばれ、一年で最も大切な行事とされています。
お盆期間中に避けるべきこと
お盆はご先祖様を供養するための期間とされており、一般的に以下のような行為は避けるべきだとされています。
- 海や川などの水辺に行くこと
お盆の時期は多くの霊が水辺に集まるとされ、「足を引っ張られる」「あの世に連れていかれる」といった言い伝えがあります。これは迷信とされますが、この時期は台風や大雨による増水など、水辺が危険になることも多いため、注意が必要です。 - 生き物の命を粗末にすること(殺生)
仏教の「不殺生戒」の教えに基づき、釣りや虫取りなど、むやみに生き物の命を奪う行為は避けるべきとされています。ご先祖様が生き物に乗って戻ってくるとも言われています。 - 引っ越し・入籍・結婚式などのお祝い事
お盆はご先祖様を供養する期間であるため、引っ越しや結婚などのお祝い事は避けるべきだと考えられています。ご先祖様の霊が戻ってこれなくなるとも言われます。 - 裁縫などの針仕事
針仕事は血を流す可能性があるため、仏教で「けがれ」とされる血を避けるという意味で、お盆期間中は控えるべきだとされています。トゲのある花を飾ることも同様に避けるべきと言われることがあります。 - 生肉や生魚のお供え
地域や宗教の風習にもよりますが、ご先祖様が好まないとされる生肉や生魚は避けるのが無難です。
まとめ
お盆はご先祖様への感謝の気持ちを伝え、故人を偲ぶ大切な日本の伝統行事です。地域の風習やご家庭の考え方を尊重し、心を込めて過ごすことが何よりも大切です。