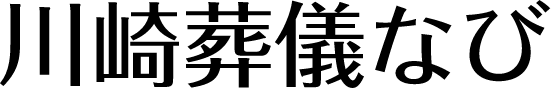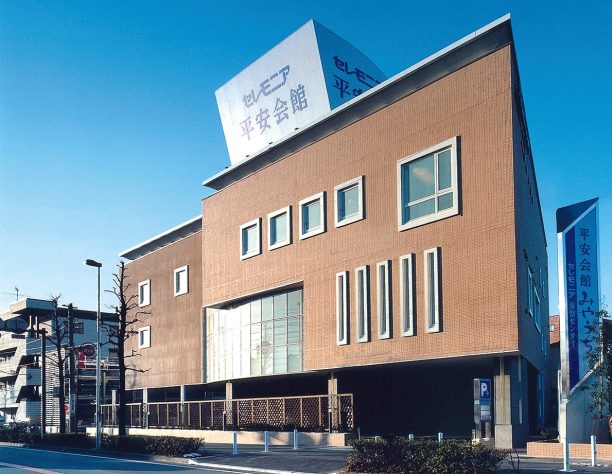戒名って自分でつけていいの?値段相場やランクについても解説

故人が亡くなった後、位牌やお墓に刻まれる「戒名」。仏の弟子になった証として授けられる大切な名前ですが、「自分でつけてもいいのか」「費用はどれくらいかかるのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、戒名に関する基本的な知識や、値段相場、ランクについて詳しく解説します。
戒名は自分でつけてもいい?
結論から言うと、自分で戒名をつけてはいけないという法律や明確なルールはありません。 しかし、戒名は故人が仏の世界で迷わずに進むために、仏様から授かる「仏弟子としての名前」という意味合いが強く、原則としては菩提寺の僧侶に授けてもらうのが一般的です。
菩提寺がある場合
まずは菩提寺の僧侶に相談することをおすすめします。自分で戒名を考えたいという希望がある場合でも、僧侶に伝えることで、その意向を汲んでくれることもあります。宗派ごとの戒名の構成やしきたりがあるため、勝手に自分でつけてしまうと、後々お墓への納骨や法要などでトラブルになる可能性もゼロではありません。
菩提寺がない場合や無宗教葬の場合
菩提寺がない、あるいは特定の宗教にとらわれない葬儀を希望する場合は、自分で戒名をつけても問題ないとされています。ただし、その戒名はあくまで「死後のペンネーム」のような位置づけになり、仏式の葬儀やお寺への納骨の際に認められない可能性があります。
生前戒名
戒名は本来、生きているうちに授かるものとされていました。現在でも「生前戒名」として、生きている間に自分で僧侶に相談して戒名を授かることが可能です。自分の希望を反映できるため、納得のいく戒名を得られるというメリットがあります。生前戒名を授かった場合は、必ず家族に伝えておきましょう。
戒名を付けない場合:俗名(ぞくみょう)での対応
近年では、特定の宗教にとらわれない葬儀や供養を選ぶ方が増えており、それに伴い戒名を付けないという選択も一般的になってきました。戒名を付けない場合は、故人の生前の名前である俗名をそのまま使用します。
戒名を付けない場合の主なポイントは以下の通りです。
- 無宗教葬や自由葬
宗教的な儀式を伴わない無宗教葬や自由葬では、戒名ではなく俗名を用いるのが自然です。故人の遺志や家族の考えを尊重した形となります。 - 公営墓地や民営霊園
寺院が管理する「寺院墓地」の場合、納骨の際に戒名がないと断られるケースがありますが、公営墓地や民営霊園であれば、戒名がなくても納骨できることがほとんどです。これらの施設は、特定の宗教宗派を問わないため、俗名での埋葬が広く受け入れられています。 - 位牌や墓石
位牌や墓石には、戒名の代わりに俗名を刻むことができます。その場合、俗名の下に「没年月日」「享年(行年)」などを記すのが一般的です。 - 法要・供養
戒名がない場合でも、故人を偲ぶ法要や供養を行うことは可能です。ただし、寺院に依頼して仏式の法要を行う場合は、事前に戒名がないことを伝え、対応が可能か確認しておく必要があります。僧侶によっては、読経は可能でもお寺の過去帳への記載ができないなどの制約がある場合もあります。 - 費用面
戒名を授けてもらうためのお布施が不要になるため、葬儀費用や供養費用の負担を抑えられるという側面もあります。
戒名を付けない選択は、個人の信仰や家族の価値観、経済的な事情など、様々な理由から選ばれています。大切なのは、故人を偲び、納得のいく形で送ることです。もし戒名を付けないことを検討している場合は、葬儀社や納骨を考えている墓地・霊園に、俗名での対応が可能か事前に相談しておくことをお勧めします。
戒名の構成とランク
戒名は、一般的にいくつかの要素で構成されており、その構成によって「ランク」が分けられます。これらのランクは、故人の生前の信仰心や社会への貢献度、寺院への貢献度などによって変わるとされています。一般的な戒名の構成は以下の通りです。
- 院号(いんごう)/院殿号(いんでんごう)
戒名の冒頭につけられる最も位の高い称号です。元々は皇族や貴族、寺院に多大な貢献をした人に贈られていましたが、現在では高額なお布施を納めた場合などに授けられることが多いです。 - 道号(どうごう)
故人の人柄や趣味、境地などを表す2文字の称号です。院号がない場合は戒名の一番上にきます。 - 戒名(かいみょう)
狭義の戒名で、一般的に故人の俗名から1文字、または仏教の経典などから1文字を取って作られる2文字の漢字です。浄土真宗では「法名(ほうみょう)」と呼ばれ、「釋(しゃく)〇〇」という形になります。 - 位号(いごう)
戒名の最後につけられる称号で、故人の性別や年齢、信仰の深さなどによって位が決まります。男性では「信士(しんじ)」「居士(こじ)」、女性では「信女(しんにょ)」「大姉(だいし)」などが一般的です。
戒名の値段相場とランク
戒名を授かる際に支払う費用は「お布施」と呼ばれ、明確な料金表があるわけではありません。しかし、戒名のランクや宗派、寺院との関係性、地域によって一般的な相場が存在します。
位号によるランクと相場(一般的な目安)
| ランク(男性/女性) | 相場 | 特徴・意味合い |
|---|---|---|
| 信士/信女 | 20万円~50万円 | 最も一般的な位号で、仏教を信仰する人につけられます。 |
| 居士/大姉 | 50万円~80万円 | 信士・信女より上位の位号で、信仰心が厚く、社会貢献した人に贈られることが多いです。 |
| 院信士/院信女 | 70万円~100万円 | 院号がついた信士・信女で、寺院への貢献度が高い場合に授けられます。 |
| 院居士/院大姉 | 100万円以上 | 戒名の中で最も高い位号の一つで、寺院や仏教に多大な貢献をした人に授けられます。 |
| 院殿居士/院殿大姉 | 100万円以上 | 院居士・院大姉よりもさらに上の位号で、特定の有力者や歴史上の人物に用いられることが多いです。 |
宗派による違い
宗派によって戒名の構成や位号の呼び方が異なり、それに伴ってお布施の相場も多少変動します。
- 浄土真宗
「戒名」ではなく「法名」と呼ばれ、「釋(しゃく)〇〇」「釋尼(しゃくに)〇〇」が基本です。位号はつけないため、他の宗派のような明確なランク分けはありませんが、「院号」がつく法名は存在し、その場合は高くなります。相場は20万円~50万円程度が一般的です。 - 日蓮宗
「信士」「信女」といった位号はつけず、「法号」という形になります。「居士」「大姉」から始まることが多く、相場は30万円~100万円以上と幅があります。 - その他の宗派(真言宗、天台宗、曹洞宗、臨済宗など)
おおむね上記の相場に準じますが、宗派特有の構成や、寺院ごとの考え方によって金額は異なります。
まとめ
戒名は故人の人生を締めくくる大切な名前です。戒名を授けてもらうためにはお布施が必要です。金額について、明確な決まりはありませんが無理をして高額なお布施を包む必要はありません。感謝の気持ちを込めて、無理のない範囲で納めることが大切です。
納得のいく戒名を授けてもらうためにも、分からないことや希望があれば、遠慮せずに菩提寺や葬儀の専門家に相談するようにしましょう。